INFORMATIONRSS
展覧会「アイノとアルヴァ 二人のアアルト 建築・デザイン・生活革命」(江東区・12/20-2/27)
世界的建築家のアルヴァ・アアルトとその妻、アイノ・アアルトが1920年から1930年にかけて追及し...MAIL MAGAZINE
ご登録はこちらから

10+1 web siteでは都市/建築に関する展覧会、イヴェントなどを紹介しています。情報掲載を希望される方はinfo@tenplusone.inax.co.jpまで情報をお送りください。なお、掲載の是非や、掲載内容、時期につきましては、編集部にて検討させていただきます。
10+1 web siteに掲載のテキスト・写真の著作権は、テキスト・写真の著者・撮影者に帰属します。
特に断りのない限り、著作権法に定められた著作物の利用規定を逸脱し、記事・図版を転載使用する事はお断り致します。
Copyright (c) 2001-2009 INAX All Rights Reserved
Powered by Movable Type 4.2
10+1 web siteに掲載のテキスト・写真の著作権は、テキスト・写真の著者・撮影者に帰属します。
特に断りのない限り、著作権法に定められた著作物の利用規定を逸脱し、記事・図版を転載使用する事はお断り致します。
Copyright (c) 2001-2009 INAX All Rights Reserved
Powered by Movable Type 4.2
200905
特集:都市計画とアートプロジェクト
都市計画としての劇場
倉方俊輔(建築史家)最後にはもっと大きな話になるので我慢して読んでほしいのだが、《座・高円寺》を訪れてもっとも感心したのは「手すり」だった。
全体を象徴する手すり

- 《まつもと市民芸術館》

- 《多摩美術大学図書館》

- 《ぐりんぐりん》

- 《座・高円寺》
劇場の前作である《まつもと市民芸術館》(2004)は、入口からの大階段が圧巻だった。劇場のフロアまで人を上げ、心理的な効果を発揮する意味では保守的と言える大階段という存在を、フロアの区別をなくし、建築を外部に解放する新しい装置として見せていた。ただし、その手すりは普通だ。なるべく目立たないようにデザインされている。時代に反旗を翻すように具体性を露わにした劇場内部の素材感は、まだ手すりには到達していなかったと言える。
《MIKIMOTO Ginza 2》(2005)は、らせん階段の復活である。入口に面した地下1階から3階までの階段が、空間をひとまとまりにしている。流れるようなステンレスの手すりは、3階の壁面から生まれ、地下1階で端部をまきこんで終わる。抽象的な空間の流動性を決定づける具体物として、手すりははっきりと意識されている。
《多摩美術大学図書館》(2007)はどうか。いわば「原スロープ」としての階段は、ここでも健在だ。1階と2階をつなぐ階段は、人のあるべき動きが固形化したかのようだ。建物の全体に閉じ込められた存在ではない。《アイランドシティ中央公園中核施設 ぐりんぐりん》(2005)を息づかせている動線と同種にさえ思える。それに拍車をかけているのが、手すりの扱いだ。一見するとシンプルながら、握り手の下端をカーブさせて落とし込む、屈曲部を避けて手すり子を取り付けるなど、細やかな配慮が見て取れる。
こうして近作を経験すると、伊東が前作までに到達したのは、全体と部分の新たな関係であり、それが階段、とりわけ手すりにもっともよく現われているのではないかという推論に至る。それは手すりのような部分を、あたかも全体の中に消去できるようなものとして処理するのではない。かといって、全体と切り離されたデザインとして、ただ遊ぼうというのでもない。
これくらいの規模の作品をてがける建築家で現在、似たような指向性を持つ者を、あまり知らない。《座・高円寺》への期待が高まるのは当然だろう。 《座・高円寺》の階段はもっとも奥まった位置にありながら、エントランスの正面に置かれているために、外部からものぞける。視線に対して開放的である。しかも、窓の少ないこの建物にあって、階段部分はもっとも明かりの多い場所である。にもかかわず、そこで露わにされているのは「暗がり」のように感じられた。
暗闇よりも確かに、闇を見せる。これは言語や論理としては矛盾だが、デザインはそれを可能にするだろう。四方八方に点在する明かりが、かえって闇を意識させ、常識的な上下左右を失わせる。こうした体験は、作者のこれまでの追求の延長線上に位置づけられ、同時に新たな一歩を踏み出していると思える。
加えて、手すりである。今度はついに木製ときた。木材を加工して、継ぎ目のない曲線を作り出している。といっても加工精度の限界があるので、多少ぎくしゃくしたカーブになる。それがまた味になる。さらに丁寧なことに、握り手の中央を少し凹ませている。こうした配慮によって初めて、階段は単なる機能を超える。触覚的にも視覚的にも、行動を支えることができる。
もちろん、私は以上を持って、単に伊東豊雄が人に対する暖かみに目覚めた「良心的な」建築家だという結論に持っていきたいのではない。こうした階段の非視覚的な具体性が、階をつなぎ、人間と建物をつないでいるという以上に、もっと抽象的なレヴェルで架け渡しているものがある。それは、この劇場に内包されているふたつのレヴェルの「都市計画」だ。
ふたつの都市計画
ひとつ目の「都市計画」とは、建物自体の構成である。劇場というビルディングタイプは、建築のなかでも花形と言っていいだろう。その場所の文化水準を示すものとみなされやすい。いわば都市の顔である。顔であるから、統一のとれた外観や固有の雰囲気を持った内部が要求される。つまり、独自の「世界」をつくることが許される。有り体に言えば、「建築」になりやすい。こうして、様式主義やモダニズムといった区分を超えて、過去さまざまな劇場の名作がつくられてきたし、今もつくられている。
しかし、本当に劇場という建築が、統合された「世界」を構築する必要があるのか? これを演劇(パフォーミング・アート)の立場から考えていくと、意外に怪しい。原理的に考えれば、世界をつくるのは建築物ではなく、演劇そのものだからである。
《座・高円寺》の構成は、そうした当然のことを露わにしているようだった。内部には3つのホールがある。ひとつのホールで公演のリハーサルを行なっている。別のホールではまったく異なる演目を練習している。そしてまた別のホールで舞台が始まると、そこでもさらに外部とは違う時間が流れる。
劇場とはなんとまあ、手に負えない類のアートを抱え込んだものだろうか。視覚芸術や聴覚芸術ならともかく、このように神出鬼没の事態を定まった形に容れようとは。複数のホールを持つ劇場は、別に珍しいものではない。しかし、《座・高円寺》のように、劇場が本来的に奇妙なビルディングタイプだと感じさせてくれる建築はそうない。
1階の「座・高円寺1」が、その最たるものだろう。芸術監督・佐藤信の考えがよく現われた、演目によって姿を変える「ブラックボックス」である。ここにおいて建築家が意匠の面で奉仕すべきは、劇場の内部にまで統一された世界を固定化するなどということではなく、むしろ各演目ごとに変わる舞台装置のデザイナーとしてということになる。
では、そこで劇場をつくる建築家は何をすべきか。設計者は賢明にも、ひとつメタのレヴェルに身を置いている。複数の個別世界を整序し、それぞれを最大限に可能にするような立場にである。3つのホールはあたかも都市の中の建築ないしは建設予定地であるかのように、与えられた条件のなかで、その面積やアクセスがうまく案分されている。それに付随する建物(けいこ場)や公共施設(ロビー)、インフラ(事務室)などと共に。
《座・高円寺》は、各ホールがまちまちの「世界」をつくることを積極的に許容した立体都市の計画である。さまざまなものを受け入れても変わらない強靱な配置をつくり出すことに、設計者の意が注がれているように感じられた。
もうひとつの「都市計画」は、《座・高円寺》が高円寺というまちの計画の一部として存在しているということだ。
1階のメインロビーの床は道路と同じレヴェルで、そこに至る扉は基本的に開け放たれており、普段はなにも置かれていない。演劇やイヴェントが行なわれない多くの時間、そこは使われていない空間として、使われている。
メインロビーに意味があるのは、その先に2階のカフェが続き、地下には区民ロビーがあるからだ。夜遅くまで営業しているカフェは、昼も照明を落とした、居心地の良い行き止まりである。道路から、なにも使われていない空間を通り、暗がりに向かって上昇する。
こうした一連のシークエンスがまちと連続し、それまでになかった体験をそこに加える。まちをひとつの世界と考えると、《座・高円寺》はその一部分として溶け込み、まちに新たな多様性を付与している。建築は強く自己を主張すると言うより、あっさりと外部に連続している。
「まちの劇場」のための階段
要するに《座・高円寺》は、外部に対してはそれ自体が高円寺というまちの「都市計画」の一部であると同時に、内部ではさまざまな劇場を整理した「都市計画」として機能している。その設計は「まちの劇場」であるという与件を真剣に受け止めたものだろう。その結果として、建築の古典的な一体感は失われざるを得ない。劇場という本来的に奇妙なビルディングタイプであるがゆえに、内部からばらばらになり、都市に連続するがゆえに、外部からもばらばらになる。それはこの劇場だけの話ではなく、現代においてすべての真剣な建築が遭遇するだろう問題と言える。
建築はただ解体されるのか。いや、そうでもないだろう。ふたつのレヴェルの「都市計画」において共通する軸となるもの、しかも、それらに解消されないような統合を可能にするものが、冒頭に触れた階段である。それは特有の存在として、異なるレヴェルをつないでいる。そうであるべく、手すりが工夫され、明かりがデザインされている。視覚的という以上に、触覚的な存在として、「都市計画としての劇場」という正しい設定を可能にしているのだ。
くらかた・しゅんすけ
1971年生まれ。建築史家。芝浦工業大学、慶應義塾大学、早稲田大学芸術学校非常勤講師。著書=『吉阪隆正とル・コルビュジエ』。共著=『伊東忠太を知っていますか』『東京建築ガイドマップ──明治大正昭和』『NA選書 手すり大全』ほか。http://kntkyk.blog24.fc2.com/


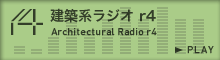

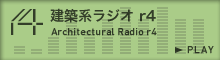



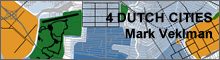
![[pics]──語りかける素材](https://www.10plus1.jp/project/assets_c/2011/10/bnr_pj_pics-thumb-220xauto-724.gif)



